 |
|||
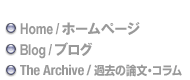
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||
|
|
シリコンバレーで通用する英語の修行法(1)
2001年7月30日[BizTech eBusiness]より
本欄担当編集者の山岸君から「いつか英語の話を書いてください」と言われながら、約束を果たせずにいた。 シリコンバレーの連中も「久しぶりに今年は夏休みを取る」という具合で、米国を流れる時間もだいぶゆったりとしてきた。ちょうどいい機会というのも何なのだが、何回かに分けて、これまで書いたことのなかった「英語の話」を書いてみようかと思う。 「入社してから英語をしっかり勉強するように」という条件付きで僕が外資系コンサルティング会社、アーサー・D・リトル(ADL)に入社したのは1987年のことだった。留学経験はもちろんないし、学生時代に英語を徹底的に勉強するというようなこともなかった僕は、「辞書を引きながら時間をかければ、まあだいたいのものは読めるけれど、話すこと、聞くこと、書くこと、つまり実践的な英語はからっきしダメ」という状態でADLに入ってしまった。 今でこそコンサルティング会社の認知度も上がって採用水準もぐっと上がったが、15年近く前は、コンサルティングの世界に入ろうという人も少なく、採用も結構いい加減な「牧歌的な時代」だったのである。 また、特にADLという会社は、他の経営コンサルティング会社と違って「技術と経営の接点」みたいなことを標榜していたため、ビジネススクールを出たMBA取得者と技術系修士取得者をあまり差別しない風土があり、英語力に対して少し寛容なところがあった。「専門さえきちんとしていれば、英語は後から何とかなるだろう」みたいな感覚が採用担当者にあったのは、僕には幸いなことだった。 ただ、当然の事ながら、入社してみるとそこは英語が溢れる世界だった。ADLジャパンの社員は日本人ばかりだった(だから英語面接がなく助かった)のだが、世界中の事務所からいつも誰かが、顧客企業のプロジェクトや日本市場調査のためにオフィスに来ていたし、海外の事務所とのFAXや電話での打ち合わせは日常業務だった。しばらくすれば海外出張もあるだろうし、英語でクライアントと仕事をしなくてはいけなくなる。 「大変なことになったなぁ」
というのが正直な感想だったが、せっかく入った会社で何とかサバイバルを図らなくてはならない、と僕は知恵を絞った。知恵を絞るには、正確な現状認識がまず必要である。当時の「僕と英語を取り巻く現状認識」は次の通りだった。
まず、とにかく困ったのは話せないことだった。当時のADLジャパンという会社は、外資系コンサルティング会社というイメージとはちょっと違う、やさしくていい人が多い家庭的な職場だった。だから、海外の事務所から短期出張で来ているコンサルタントたちを暖かく迎えるために社員全員参加のパーティを開いたり、近所にランチに行くときは、プロジェクトとは関係のない若い社員を誘ったりしてくれた。ここでとにかく話ができないのである。 だから入社してまずやったことは、自己紹介の文章を、時間をかけていくつか書き、それを先輩や、海外事務所から来ているコンサルタントに添削してもらい、全部暗記してしまうことだった。 僕の「選択と集中」サバイバル戦略の最初の目標は、「自己紹介だけは徹底的にうまくなること」「自己紹介に関わる想定質問には、追加質問がなるべく来ないような、うまい返答を用意しておくこと」「相手からの質問ばかりが長く続かないように、こちらからの定型質問をいくつか用意し、機をみて身をかわす構えを作ること」だった。 だいたいパーティの席や大勢でのランチの席で、僕が初対面の誰かと英語で1対1で話をしてぼろが出ないようにしなければならないのは、長くても5分というのが僕の判断だった。5分ならばこれで乗り切れる。何せ最初はどんなときも自己紹介から始まるのだから。5分リングに立っていれば、ゴングが僕を救ってくれるだろう。 こんな風にして、僕の英語修行が始まった。 ■
|
|
|
|
||
| ページ先頭へ | ||
| Home > The Archives > BizTech eBusiness | ||
|
|
|
© 2002 Umeda Mochio. All rights reserved. |