 |
|||
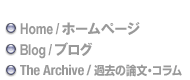
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||
|
|
GOLD RUSH 1996年8月1日[日経BPムック インターネットビジネス最前線]より ビジネスのルールを一変させてしまう可能性を持つインターネット。 アメリカでは、インターネット・ビジネスの現状を、19世紀のゴールドラッシュにオーバーラップさせる見方がある。インターネット起業家達の中心地シリコンバレーと当時のゴールドラッシュの中心地が同じカリフォルニアであること、「早いもの勝ち」という感覚が極めて強いこと、フロンティア精神・起業家精神が横溢していること、何よりも短期間に富が創りだせる予感−−−。そんな諸々のことが合わさって、アメリカ人たちはゴールドラッシュ時代に思いをはせるのだろう。 カリフォルニアで金が偶然にも見つかったのは、1848年の1月だったという。同じ年の6月にはサンフランシスコの街から人が消え、誰もが「金を掘りに行く」という看板を掲げて家や店を閉めてしまい、街はゴーストタウンさながらの状況になったという。そしてその翌年(1849年)はゴールドラッシュ最盛期となり、東海岸からも大挙して人が押し寄せた。 1848年1月から1850年1月までの2年間のゴールドラッシュに関する新聞記事をそのまま集めて編集された本がアメリカで出版されている。それを読んで、当時の雰囲気が、現在のインターネット世界の興奮にとてもよく似ていると思った。金を掘りに出掛けていってしまった百数十年前のサンフランシスコの人たちと、インターネット・スタートアップ(インターネット関係の出来たばかりのベンチャー企業をこう呼ぶ)を最近興した人たちは、「居ても立ってもいられなくなって」という気分においてそっくりである。 インターネットは、コンピューター産業の世界の出来事だというのは間違いである。確かに、コンピューター産業の第1世代(メインフレーム)、第2世代(パソコン=PC)に続く第3世代がインターネットであることは事実である。しかしその社会全体に及ぼすインパクトの大きさという面からいえば、第2世代までは単に「コンピューター産業というコップの中の嵐」だったのに比べ、インターネットの第3世代は、そのコップから何かが洪水のように流れ出て、外界(コンピューター産業以外の産業)にとてつもなく大きな影響を及ぼす予感に満ちている。それを多くの人が直感的に感じているからこそ、インターネットにこれだけの注目が集まっている。 コンピューター産業の歴史からいえば、第2世代(PC)の萌芽期が1981年前後だったのと同じ意味で、現在は第3世代(インターネット)の萌芽期といえる。しかし第2世代の萌芽期には、PC産業をゴールドラッシュになぞらえる声などなかったし、世間の注目度もそれほど高くなかった。インターネットとPCとでは、その「可能性空間」が全く異なるからなのである。 なじみの無い言葉かもしれないが、産業の萌芽期にその「種」を見つめて将来の「可能性」を考えた時の「広がり」の度合いを「可能性空間」と称してみたい。第2世代(PC)の萌芽期から約15年が経過して、ほとんど何も無いところから驚異的スピードで何十兆円という規模の産業が生まれたわけだが、その萌芽期、この巨大産業の「種」は、「性能の低い不満だらけのスタンドアローンPC」だった。そこに「可能性」を見出し、新しい事業機会を追求した人たちの創造性こそが、現在の何十兆円という産業を創りだしてしまった。 「性能の低い不満だらけのスタンドアローンPC」を「種」とした第2世代(PC)と、「当時の何万倍もの性能を持つ現在のPCが何千万台、何億台という単位で相互接続されている環境」を「種」とする第3世代(インターネット)とを比べれば、その「可能性空間」が、スケールの面で全く異なっていることがわかると思う。
インターネットにおける「ゴールド」とは何か 「世界中の人々、企業、情報がネットワークでつながっている」という環境から創りだされる「全く新しい価値」こそが、インターネットにおける「ゴールド」だと思う。「人とマネーとのかかわり方はどう変わるのか」「人と人が知り合ってコミュニケーションを取る方法にどんな新しさが生まれるのか」「人が何かを学びたいと思った時にまず考える勉強の仕方はどんな風になるのだろうか」など、人の生き方、生活の仕方、仕事の仕方、楽しみ方、ありとあらゆる場面を考えていった時、新しいネットワーク環境の中で「人々にとって全く新しい価値」が創造されるわけで、それがインターネットにおける「ゴールド」である。ただ、今はまだ、その可能性についてあれこれ論じられ、試みられてはいるが、本当に見つかってはいないという段階である。ブラウザーにしてもJavaにしても、コンピューター産業の側から提供される製品は、「全く新しい価値」を創りだすための「道具」に過ぎない。 ゴールドラッシュで富を創りだした人達にも同じように、2つのタイプがあった。1つはもちろん、金鉱を掘り当てた鉱夫達。もう1つは、鉱夫達に、道具やサービスを提供した人たちである。後者の代表例には、鉱夫達にジーンズを提供したリーバイ・ストラウス、金や手紙を安全に必要な場所に配達するサービスなどを提供したウェルズ・ファーゴ社がある。(ウェルズ・ファーゴ・バンクは現在全米第17位の銀行)。 ただ、百数十年前のゴールドラッシュと現在のインターネット・ゴールドラッシュでは、本質的なところで全く違う点が1つある。それは、「道具やサービスの提供者」と「金鉱を掘ろうとする人たち」のどちらが先に存在したかという違いである。本物のゴールドラッシュは、ゴールドが発見され「金鉱を掘ろうとする人」が先に生まれ、「道具やサービスの提供者」はそれについていった。だからわかりやすかった。 一方、インターネット・ゴールドラッシュの場合は、ハイテク産業の常でもあるのだが、「道具やサービス」の方がより先に提供されつつある。使い道がはっきりする前に、道具ばかりがどんどん進化している状況といってもいいかもしれない。そしてそこに注目が集まっている。だから、ネットスケープのブラウザーやJavaのような道具が、「ゴールド」であるかのように見えてしまう。しかし本当の「ゴールド」は、今提供されつつある「道具やサービス」を使って、さあこれから探しましょう、という状況なのである。
「ゴールド」はどこに埋まっているのか ただ一方、冷静になって考えてみれば、こうした「新しい価値を創造する事業」が生まれたところで、金を支払う側の論理としては、たとえば、増収のない家計で支出が莫大になるはずがなく、今使っている支出の使い道を少し「新しい価値」の方にシフトするだけである。つまり、「新しい金融サービス事業」や「新しい小売事業」がネットワーク環境を前提に生まれれば、「既存の金融サービス事業」や「既存の小売事業」に払っていた支出が、新しいサービスにシフトするのである。 たとえば私はアメリカに引っ越してくる時に、自分の銀行口座を日本の都市銀行から米シティバンクの東京支店に移してしまった。日本円で支払われた給料の一部をドルに変えて米国の銀行に送金する手続きが、電話取引で極めて簡単にできて便利だったからである。銀行口座に預ける金の総量が変わったわけではなく、単にシフトが起きただけである。こんな程度のことよりももっと大掛かりに「新しい金融サービス事業」が生まれるとすれば、そしてそれが「ゴールド」なのだとすれば、「既存事業」の側の失うものはかなり大きいということになる。 1994年末に、「クイッケン」という家庭用財務ソフトで全米80%以上のシェアを持つインテュイット社をマイクロソフトが買収しようとしたことがあった。当時、マイクロソフトの独占に対してコンピューター産業全体が敏感になっていた時期だったので、司法省の横やりが入って、結果として買収断念ということになった。 ただ実際には、危機感を強く持った米国金融業界が、買収阻止を目的としたロビー活動を行ったと噂されている。マイクロソフトは、「電子財布」(エレクトロニック・ウォレット)という将来構想を持っており、電子財布に付随した「新しい金融サービス事業」を模索しているわけだが、それに対して金融業界という「既存事業」側が危機感を持ったことは自然な流れだったのである。 インターネットによってそのビジネスの仕組みが大きく変わり得る産業だけ見ても、小売産業は1兆5,000億ドル(約158兆円)、教育産業は5,000億ドル(約53兆円)、金融サービス産業と広告産業で2,700億ドル(約28兆円)、ヘルスケア産業が7,400億ドル(約78兆円)、などなど莫大な既存産業がある(数字は資産、米国市場のみ)。こうした売り上げ規模のほんの1%が新しいサービス側に流れたとしても、その金額は莫大なものとなる。それがだんだん数%と上がっていけば…。インターネットにおける「ゴールド」とは、こうした既存産業の莫大な売り上げの中に埋まっているものだと考えればよいのである。
「ゴールド」は誰が掘り当てるのか シナリオA: インターネットは、技術手動で道具が先に準備されてきた。新しい価値の創造も、新しい道具を作り出せるほどに技術を知り抜いているIT(情報技術)産業の側が行うに違いない。その証拠に、既存事業の動きなど遅々としたもので、インターネットのことなど何も知らないではないか。道具を提供する事業に加えて、「ゴールド」を掘り当てるのも、IT産業側である。 シナリオB: 新しい価値の創造は、既存産業や顧客を知り抜いていることが成功要因である。IT産業から提供される道具(通信インフラ、ブラウザー、Java、セキュリティ・ソフト等)を駆使して、既存産業側によって新しい価値の創造が行われるに違いない。「ゴールド」を掘り当てるのは、危機感を募らせた既存産業側である。いずれにせよ、IT産業はインターネット・ゴールドラッシュの道具提供者に過ぎないのだ。 シナリオA場合、大手企業といえば、IBM、マイクロソフトといったIT産業で既に重要な役割を果たしている企業群であり、ベンチャー企業といえば、ネットスケープ、ヤフーのような技術志向のインターネット・スタートアップ企業群である。 シナリオBの場合、大手企業には、様々な既存産業を押さえる大手企業がすべて入るし、ベンチャー企業には、特に技術を持たなくとも顧客志向で新事業を起こそうとするインターネット・スタートアップのすべてが入る。 もちろん、この戦いは、まだ始まったか始まらないかという状況にあり、一般論として誰が勝つかを論ずる時期にはない。 ただ一つだけいえることは、IT産業側、既存産業側を問わず、ベンチャー企業群のスピードが早く、激しいことである。F1的スピードで走り出したというイメージだ。 多くのベンチャー・キャピタリストが、投資しているインターネット・スタートアップ企業に対して、「とにかく死に物狂いで働いて、人より一歩でも二歩でも前へ早く進め」という雰囲気の指示を出しているという噂を最近よく聞く。「骨は後で拾ってやるから走れるだけ走れ」といった感じなのだろう。ここでもまた、ゴールドラッシュ時代に、高い給料を出してでもたくさんの鉱夫を雇ってゴールドを堀りに行かせた金持ちの姿が思い浮かぶ。 既存事業の売り上げを強奪しようという「ゴールド」を目指す動きは、インターネット上のいろいろなウェブサイトを見に行けば、誰でも実感することができる。それも1回だけではなく、1週間おきに同じウェブサイトを定点観測したり、ある1週間の間に新しく生まれたウェブサイトを見に行ったりすると、ものすごい量の活動が短期的に行われていることが実感できると思う。
新しいタイプの人材が流入する しかし、ネットスケープは昨年、極めてユニークな大物経営者をCEOに迎えた。ジム・バークスデール、53歳。情報技術を駆使した斬新な経営手法で、フェデラル・エクスプレス社を大きく成長させた実績を持つ経営者である。当時、ネットスケープのCEOに誰が就任するかは、業界では注目の的であった。ネットスケープの将来はほぼ約束されたように思われていたし、そうならばCEO就任というのは、仕事の重要さもさることながら、個人資産という意味で莫大な約束手形を保証されたようなものだったからだ。 フェデラル・エクスプレス社は、日本でいえば佐川急便やヤマト運輸のような宅配業者である。フェデラル・エクスプレス社は、インターネットがこれだけ騒がれる前から、情報技術を駆使して、顧客が配達を依頼した荷物が現在どこまで運ばれているのかを瞬時に把握することのできるシステムを開発した。顧客はいつでも自分の荷物がどこにあるのかを問い合わせることができるようになった。このサービスは顧客満足度を高め、企業は大きく成長した。ジム・バークスデールは、この新サービスを構想し実現した時のCIO(情報システム部門責任者)である。 ジム・バークスデールは、IT企業の典型的な技術志向の経営者ではない。むしろ情報技術は道具ととらえ顧客志向を貫くことでの成功体験を持つ希有な経営者といった方がいい。そのバークスデールがCEOとなったことで、インターネット世代の旗手・ネットスケープは、既存産業の莫大な売り上げの中に埋まっている本当の「ゴールド」を求めて、新しい挑戦を始めたのかもしれない。 マイクロソフトがIT産業のみならず、新しい事業に旺盛な関心を示し、様々な手を打っていることはよく知られている。新しいタイプの「オンライン雑誌」という分野もその一つで、雑誌を大きな収入源とする出版産業に対する挑戦とも言える。マイクロソフトはその、「オンライン雑誌」構想を進めるために、マイケル・キンズリーという有名なジャーナリストを招聘した。いくつかの雑誌編集長を経験し、ワシントンでの政治記者としての経歴も長く、CNNの政治討論番組「クロスファイヤー」のホスト役も勤めた人である。誤解を恐れずに言えば、日本のコンピューター企業が、田原総一郎を新事業部門のトップにヘッドハンティングしたような感覚かもしれない。 いろいろな意味で、シナリオAを実現しようとするIT産業側の攻勢は鋭い。多様な優れた人材がIT産業に流入してきて、今までは思いつかなかったような斬新な戦略が実施されるのではないかと思われる。
「勉強してから」では間に合わない どんな産業のどんな企業にも「ゴールド」を掘り当てるチャンスがあり、それを逸すれば、競合企業やIT産業といった敵から顧客を奪われてしまう危険が伴う。そんな意味でインターネット環境が整備されてくるに伴い、「10年に1度の経営革命」が始まるのは必然なのだと思う。日本はアメリカよりもインターネット環境の整備は遅れるだろうが、着実に現実のものとなってくるはずだ。 この時期にあたって、日本企業にとって重要なことは、「思いついたことは、とにかく何でもどんどんやって見る」ということのように思う。いい加減な言い方に聞こえるかもしれないが、インターネットの世界は、その「可能性空間」が大きいことについては誰もが理解はしたが、それ以上のことは実は誰にもよくわかっていないという「偉大なる混沌」とでも言うべき様相を呈している。何かを始めることは簡単で、何かを始めると、何かが見えてくる。何も始めないと、何も見えてこない。私の専門は、コンピューター企業への経営コンサルティングなので、日頃お付き合いするのは、日本のコンピューター企業のトップやミドルの方々が多い。その中で、過去に「絶対に故障してはならないシステム」とか「念には念を入れた設計が必要な巨大システム」とかの重要な事業を担当された人ほど、そしてそれが優秀な人ほど、いい加減に何かを始めることに抵抗感が強い。将来が不確実で何かをやってみないと次のステップが見えてこないことが頭でわかっていても、身体が動かない。例えば、まず「インターネットの世界で何が起こっているのかを勉強しよう」とする。でも勉強の対象は、時々刻々と進化を続けている 勉強すればするほど、わからないことが増えてくる。だから行動に移すタイミングを逸して、ずっと勉強し続けてしまうことになる。キャッチアップ型でよかった時代は、徹底的に勉強して、すべてを理解して、絶対に成功すると確信してから、おもむろに行動に移せばよかった。しかしインターネットの世界で、その行動パターンは通用しない。こうした例はコンピューター企業に限らず、日本の大企業のいたるところで見受けられる。 経営革命とは何も新規事業のだけのことではないのだが、例えば新規事業の場合、その芽というのはいつも小さく、それを心から面白いと思って、全力疾走できるかどうかが成功の鍵を握る。数千億円、数兆円という売り上げ規模を誇る大企業が、数億円の事業に興味を示さず全力疾走できない間に、たった数人のチームが小さな新しい事業を作ることに興奮し、全力疾走して何かをやり遂げてしまう。これがアントレプレナーシップ(起業家精神)である。
世界には、インターネットをゴールドラッシュのように感じて、居ても立ってもいられず何かを始めた人達がたくさんいる。嫌々何かを始めるのではなく、「居ても立ってもいられない」といった気分で、日本企業も何かを始めてみてほしい。起業家的人材を見つけて、活躍の場を与えて、いろいろとチャレンジしてみれば、道は必ず開けてくると思う。そしてそのためには、スピード、個人の才能、リスク・テイキングを尊重した新しい経営スタイルが必要となってくる。そんな試行錯誤の中から「10年に1度の経営革命」は始まるのだと思う。
■
|
|
|
|
||
| ページ先頭へ | ||
| Home > The Archives > 日経BPムック インターネットビジネス最前線 | ||
|
|
|
© 2002 Umeda Mochio. All rights reserved. |