 |
|||
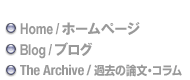
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1999年のIPO(株式公開)ラッシュを考える
2000年2月2日[コンセンサス]より
起業家主導型経済システムの席捲 そして、このニューエコノミーを力強く支える「新しい社会の仕組み」として、起業家主導型経済システムが、米国で本格化した年だったと言えよう。 起業家主導型経済システムのモデルは、昔からシリコンバレーには存在していた。しかし、シリコンバレーはある狭い分野で世界の最先端を走ってはいたが、決して米国経済のメジャーストリームを担う存在ではなかった。世界の片隅で、世の中全体とは全く違うルールで、そのルールを好きな連中だけが、情報技術に関わるフロンティアを探求していたに過ぎなかった。私が5年ほど前にシリコンバレーにやってきたのも、この世界がただただ好きだったからだ。 しかし、PC時代からインターネット時代に移り、その及ぼすインパクトが巨大で、広がりも社会全体に及ぶに伴って、シリコンバレーの起業家主導型経済システムが、米国経済のメジャーストリームに踊り出て、強い影響を及ぼすようになった。 「Internet economy has become a U.S. economy.」(インターネット経済が、米国経済そのものになってしまった) そんな言葉さえよく耳にするようになった昨今、それがさらにグローバルスタンダードに姿を変えて世界を席捲しようとしている。 起業家主導型経済システムは、勝者と敗者をくっきりと分け、才能のある者は才能のある者とより強く結びつき、それが富に直結する過酷な世界だ。富める者はより富んでいく。ネットに対応できない人たちの将来は決して明るくない。 シリコンバレーという狭い世界で限定的に通用してきたこのルールが、グローバルスタンダードになって、本当に世界中の人々が幸せになるのか、この変化が地球全体にとって本当に良いことだったかどうかは、後世の歴史家の判断に委ねられるべき問題であろう。しかし、もうこの流れをせきとめることはできないのである。 1999年の米国IPOラッシュの背景には、こんな大きな革命的変革の潮流が存在している。現在の株高にバブル的要素が含まれているのは誰もが承知の上で、バブル崩壊が仮にあっても「もうオールドエコノミーに戻ることはない、盛り返す力もニューエコノミー側にしかあり得ない」と心から信ずるようになったのが1999年だったのだ。
歴史的IPOラッシュ 99年が歴史的であったポイントは4つある。
第1に、IPO企業の株式公開後の株価上昇である。 順に議論していこう。なおここでIPO企業という場合は、大企業からのスピンオフは含まず、ゼロからスタートして株式公開を目指す純粋なスタートアップ企業を指すこととする。
表1 IPO企業の株価上昇ベスト10
まず、IPO企業の株価上昇について見ていこう(表1)。ここがバブル経済と揶揄されるゆえんであるが、第1位のInternet Capital Group社 (以前に本連載「インターネット投資会社の登場」で触れたインターネット投資会社)の株価上昇率は、2,733%。この数字の読み方は、100%上昇が「2倍」で、200%上昇が「3倍」の意味だから、2,733%は「28.33倍」の意味である。表中、年末の株価を公開価格で割っても、うまくリターンの数字と合わないものもあるが、それはすべて株式分割が行われた企業の場合である。
出典:Hoover's Online 余談になるが注目は、投資会社であるInternet Capital Group社を含めベストテンの半分までが「B2B」(Business to Business)のeコマース関係で占められていることだ。99年が「B2B」の年だったことがこの数字からもうかがえる。本連載でも何度も触れたオープンソースのRed Hat社もベスト10入りした。
さて第2に、IPO企業が株式公開時に行った資金調達の額である(表2)。 表2 IPO企業の株式公開時の資金調達額の推移
スタートアップ企業ではないのでこの表には掲載しなかったが、大型書店Barnes & Noble社がAmazon.com社に対抗するためにスピンオフしたBarnesandnoble.com社は4億5,000万ドルの資金調達を行ったし、投資会社Donaldson, Lufkin & Jenrette社(DLJ)がオンライン証券事業のためにトラッキングストックを発行して調達した資金は、3億2,000万ドルに上っている。
そして第3に、IPO企業が株式公開前に調達した資金の額も急増した。これはベンチャーキャピタル・ファンドの総額が大きくなったこととも関係するが、以前は大企業にしか構想できなかったような「巨大な投資を必要とする新事業」の仕込みを、株式公開前に行うことができるようになったことを意味している。株式公開時に3億7,500万ドルの資金調達を行ったWebvan社は、株式公開前にもほぼそれと同額の資金調達を行っており、これは過去の常識を大きく覆した。
象徴的なWebvan社 その象徴が、Webvan社なのである。Webvan社は、米国インターネット産業史上「最も大胆で最もリスキーなギャンブル」と評されるスタートアップ企業であるが、狙いをつけるのはグロサリー市場。日本語訳すれば食料品雑貨となるが、コンビニとスーパーで売っているもの全部をイメージすればよい。米国グロサリー販売の市場規模は、5,000億ドル(約55兆円)。そのうちの5%から10%がeコマース化しただけで、数兆円規模の新市場が出現することになる。本やCD販売の市場規模がそれぞれ100億ドルから150億ドル程度であることに比べれば、その可能性の巨大さがわかる。 そしてWebvan社のビジョンは、「最新技術をぶちこんだ巨額の投資を行って巨大自動化倉庫を構築する」ことで差別化をはかり、グロサリー流通産業の姿を変えてしまうことである。 1996年に設立され99年6月にサンフランシスコとシリコンバレー地域に限定したサービスを開始したばかりのスタートアップ企業でありながら、Webvan社は、サービス開始から1ヵ月後の7月に、大手エンジニアリング会社・Bechtel社に対して、全米20数カ所に最新鋭倉庫を建設するという総額10億ドルの発注を行っている。その発注を行った時点での売上はまだほんのわずか、100万ドルにも満たなかったわけで、その発注はすべてこの巨額な資金調達によってまかなう算段なのである。こうしたスタートアップ企業は過去になかった。全く新しい現象と呼んでいいのである。
日本のスタートアップ企業もIIJ社に続け その筆頭に、日本を代表するスタートアップ、IIJ社(インターネット・イニシアティブ)が挙げられるのは、とてもうれしい限りである。 1999年8月にナスダックに株式公開を果たしたIIJ社。23ドルの公開価格が年末までに97.19ドルまで上昇した。公開時株価23ドル時点での時価総額10億ドルは、年末には42億ドルにまでアップした。立派なナスダック企業に仲間入りである。 ところで99年は、米国発ニューエコノミーの大潮流が、とうとう日本にも本格的に波及してきた年だった。99年6月頃から提唱されはじめたナスダックジャパン構想に端を発し、99年2月にサービス開始されたiモードの爆発的普及、通信料金定額制論議の沸騰、東証マザーズの創設と、2000年のインターネットシーン変貌を予感させる動きが急である。 しかし慶應義塾大学の国領助教授は、「最近気になるのはネット関連の創業間もない企業への異常とも言える投資意欲の高まりだ。数少なく経験浅い起業家のまわりに巨額の投資資金が流入し早くもバブルが発生しているように見える。近い将来、実質的な内容に乏しい会社の株に、上場前後に法外な値がつき、後に暴落して多くの投資家が大損する事態が多発する恐れがある。自己責任で損をする投資家がでること自体は必ずしも問題視すべきではない。むしろ反動でネットベンチャーに対する投資が冷え込む事態が心配だ」(日本経済新聞99年12月27日経済教室)と指摘する。 また日本経済新聞・野村裕知編集委員は、日米ネット株には3つの差があると指摘する。第1は投資の物差しの差。米国ネット株が割高と批判されながらもそれなりの投資の論拠が築かれてきた。日本にはそれがない。第2は調整の差。この5年間米国では小規模ながらも調整に次ぐ調整が続いてきた。日本はまだこれから。第3は厚みの差。米企業は株式公開すると分割を繰り返し株主を増やすが、日本では浮動株が少ない有力銘柄さえあるという。そんなことから、『目先「過熱」への警戒が必要なのは米国ではなく、日本ではないか』(日本経済新聞1月12日)と結論付ける。 私も、バブル懸念含みの米国ネット株に比べてもはるかに高い株価が、マザーズ公開2銘柄を含めてさほどの成長性も予感できない日本のスタートアップ企業に対してついていることは事実であり、とても危険なことだと思う。その意味で、国領助教授、野村編集委員の指摘は時宜を得た重要なものと考える。 日本にベンチャー株式市場がだんだんと整備され始めたことはそれ自身朗報だが、せっかくのIIJ社の快挙もあったことだし、より高い目標を持って米国ナスダック市場に公開する日本のスタートアップ企業がこれから増えていくことを心から期待している。 ■
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページ先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home > The Archives > コンセンサス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
© 2002 Umeda Mochio. All rights reserved. |