 |
|||
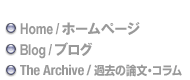
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|||
|
|
インターネット時代のMicrosoftを考える
1997年6月1日[コンセンサス]より
会社が少しうまくいったら高値でMicrosoftに売却してしまおう WebTV設計・開発の約300ドルの箱(最終製品はソニー、Philips製)を買って、月額20ドルの接続サービスを申し込めば、PCを持っていなくても、インターネットが家庭のテレビから使えるようになる。つまり簡単に言えば、テレビの世界とインターネットの世界を融合させる技術を持ち、一早くサービス事業化したのがWebTVである。 MicrosoftによるWebTV買収総額は、4億2500万ドル(約500億円強)と巨額なのだが、WebTVの設立は95年6月であるから、2年間足らずの活動成果が500億円の価値を生んだ勘定になる。驚異的な数字といっていい。 昨年の今ごろ(96年4月)は、Yahoo!社の株式公開(IPO:Initial Public Offering)が話題となっていた。そしてその約半年前の95年8月には、設立後1年数カ月というスピードで、Netscape社が株式公開した。そう、一昔前まで、いや、一昔といっても半年か1年前までは、ベンチャー企業は株式公開を目指すのが当然のことだったのである。 でも今は様子が違う。ベンチャー企業が全力で数年走り続けた成果を、Microsoftが買収してくれるという選択肢がはっきりしたからである。ベンチャー企業が初期の成功の代償を現実のもの(実際には現金)にする手段の中から何を選ぶか、専門的には「ベンチャー企業のExit Strategy」と言うが、「Microsoftに自社を売却する」ことが、この「Exit Strategy」の有カオプションの一つになったのである。 実際、Microsoftは、96年1月から12月までの1年間に、約8億ドル(約1,000億円)を投入し、20社のインターネット関連ベンチャー企業を対象に、買収または資本参加を行った。2~3週間に1社の割合といえ、驚異的である。主だったところだけでも、Web文書ツール「Front Page」のVermeer Technologies社の買収(96年1月)、インターネット・コマース・ソフトのeShop社の買収(96年6月)、WebマネジメントツールのNetCarta社の買収(96年12月)が挙げられる。 すべての大企業がそうだというわけではないが、Microsoft以外にも、ベンチャー企業の買収に積極的な企業がいくつかある。ネットワーク・インフラ市場で圧倒的シェアを誇るCiscoSystems社や3COM社がその好例である。 つい先日、ネットワーク・インフラ関係のベンチャー企業やベンチャー・キャピタリストが集まる会議に出席した時のこと、最も注目を集めていたのは、ギガビットEthernet関係のベンチャー企業数杜であった。ただ少し驚いたのは、業界関係者が、「この中の誰が、いつ、Ciscoに買収されるのだろう」と真剣に議論していたことであった。Ciscoによる将来のギガビットEthernet企業買収は、もう業界では織り込み済みの「規定事実」となっているのである。つまり、逆に言えば、「Ciscoへの自社売却」という選択肢は、ギガビットEthernet関係のベンチャー企業の「ExitStrategy」の有カオプションの一つになっているわけである。
Microsoftの大戦略転換 エコノミスト誌(97年3月29日号)も、「ビル・ゲイツは当初、インターネットの意義を過小評価したが、誤りに気づいた後、アメリカの企業史でも最もドラマチックな転換(Turnaround)を行なった」と高く評価している。Microsoftがベンチャー企業買収にこんなに積極的になったのも、こういう大戦略転換の一環としてなのである。 コンピュータ産業の歴史はたかだか50年というところであるが、現在は、第2世代(PC)から第3世代(インターネット)への移行期である。このことは4月号で詳しく述べた。 そして約15年前から始まった第1世代(メインフレーム)から第2世代への移行においては、第1世代の勢力(IBM,DEC等)が第2世代勢力(Intel,Microsoft等)に敗れ、大きな痛みを経験した。世代交代の際には競争のルールやビジネスモデルが変わるから、業界支配者が変わるのも必然であった。 では第2世代から第3世代にかけても、同じことが同じように当てはまるのだろうか。 ビル・ゲイツはあるとき、自分が過小評価していたインターネット世代の台頭を目のあたりにして、背筋がぞっとするような戦慄を覚え、「第2世代勢力に敗れた第1世代勢力の二の舞になってたまるか」と強く誓ったのに違いない。 ビル・ゲイツが、95年5月こ、Microsoft幹部に送った電子メールの文面は次のような文章で始まっている。『The Internet is the most important single development to come along since IBM PC was introduced in 1981.』(インターネットは、1981年にIBM PCが登場して以来、最も重要かつ唯一の開発である) 遅まきながら、ビル・ゲイツがついにこの事実を認めたのが、95年の5月だったのである。 94年10月に、私は日本からシリコンバレーに引っ越してきたのだが、その当時、Microsoft関係で大きな話題になっていたのは、Windows 95リリースと、家庭用財務ソフト大手のIntuit杜を買収しようとして司法省の横やりが入りだしていたことと、いよいよMSN(MicrosoftNetwork)をもってオンライン・サービス事業に参入するという話の3つであった。 インターネットのイの字もなかったのである。時すでに、Netscape Navigatorがリリース(94年11月)される寸前であった。当時水面下で開発が行なわれていたJavaがアナウンスされるのがその半年後の95年5月であるから、当時のMicrosoftの動きがいかに遅かったかがわかる。
もともとMicrosoftという会社は、他社に先駆けて斬新なコンセプトを出す会社ではなく、「市場動向を見極めてから動く」という戦略でここまでやってきたから、インターネットも同様で、ことさらに珍しいことではないと言えるのかもしれない。しかし、そうだとしても、「これまでとは様子が違うから、全く新しい経営をしていかなければ追い着けない」とビル・ゲイツは腹をくくったのであろう。
94年4月に「Mosaic」を開発したマーク・アンドリーセンらがNetscapeを設立する。その7ヵ月後にNavigatorをリリース、その10ヵ月後には株式を公開する。その2ヵ月後のCOMDEXで、「$500 PC」、今でいう「ネットワーク・コンピュータ」(NC)のマンセプトが発表される。 このインターネット時代の新しいスピード感の中で、何周か遅れでレースに参戦する感覚をビル・ゲイツが抱いたとして何の不思議もない。 しかしそれからのビル・ゲイツの動きは速かった。95年5月のゲイツの電子メール以来、今までにまだ2年しか経過していない。現在つまり97年4月に、インターネット世代の旗手「Netscape」の将来を危ぶむ声が出ているなどと、当時の誰が想像できただろう。インターネット関連の超有望ベンチャー企業群が「自社をMicrosoftに売却」して喜んでいるような姿を、誰がイメージできたことだろう。 だが、そんなことがMicrosoftの大戦略転換・巻き返しの急により、現実に起こっているのである。
「Excecution」の時代に凄みを増した感があるビル・ゲイツ なぜ今そんな言葉がよく使われているのか。 理由は簡単だ。 「やるべきことははっきりとし、何をやるべきかをそれほど悩む必要もなく、やると決めたことを粛々と実行していくだけ」という時代に入ったからである。 93年は「マルチメディア」、94年は「情報スーパーハイウェイ」。当時は、将来の姿をキーワードに託して、その姿を描きたいと思っていた時代だった。そしてそんな悠長な時代はもう終わったのである。ビル・ゲイツが『The Road Ahead』(日本語版は『ビル・ゲイツ、未来を語る』)を書いていた当時は、今からいえば「古き良き時代」である。 Microsoftの大戦略転換は、戦略転換自身に価値があるというよりも、その「Execution」に価値があったと言うべきであろう。 仮にトップレベルで大戦略転換を意思決定したとしても、「Execution」能力がなければ何の実効も出ない。たとえば冒頭に紹介した「インターネット関連ベンチャー企業の買収」も、コンセプトよりもむしろ買収後のマネジメントに、本当の価値がある。たとえば、買収したは良いが、最も優秀な人たちが辞めていってしまったのでは、何の意味もない。その対策のために、特別HR(Human Resource:人事)チームを発足させ、買収企業の人材確保と動機付けに当たったりしている。 Microsoftという大企業の、大開発部隊を、大マーケティング部隊を、経営幹部の発想法を、新しい方向に転換させるのは、かなりの力技である。それをいとも易々と、トップのリーダーシップでやってのけたところに、「Execution」という視点でのビル・ゲイツの凄みがある。 しかし、シリコンバレーの創造的な人々は、ビル・ゲイツが好きではない。「自分で何も新しいものを生み出していないくせに、業界を支配しているから」というのがその理由だ。 そう、でも逆にいえば、昔から「Execution」に優れた企業だったMicrosoftが、今再び光彩を放っているのも、現在が「Execution」の時代となったことを象徴していると言えるのであろう。 ■
|
|
|
|
|
|||
| ページ先頭へ | |||
| Home > The Archives > コンセンサス | |||
|
|
|
© 2002 Umeda Mochio. All rights reserved. |