 |
||
|
|
||
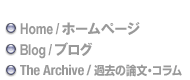
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
その後のオープンソース
1999年4月7日[コンセンサス]より
オープンソース・脚光を浴びる まずこの半年の流れを、時系列で追いかけていくことにしよう。それ以前のオープンソース史については「オープンソースとは何か」をご参照いただきたい。 昨年後半、Linuxの飛躍にはずみをつけた最大の出来事は、「9月29日、Linuxの販売・技術サポートを手がけるベンチャー企業、Red Hat Software社に、ベンチャーキャピタル2社と共に、Intel社とNetscape社が資本参加する」という発表であった。このニュースは日経産業新聞が一面で取り上げるほど、日本でも注目を集めた。 Intel社がMicrosoft社と競合するRed Hat Software社に投資したという事実は、Intel社がMicrosoft社から少し距離を置き、独自の道を歩み始めたことを意味し、新しい時代の到来を感じさせる出来事であった。 Red Hat Software社は、この投資で得た資金で「enterprise support division」という部門を新設し、大企業のLinux導入を積極的にサポートしていく体制を整えた。 その後も、IT産業のメジャープレーヤたちが、続々とLinuxへのコミットメントを示し(表参照)、3つのタイプの新しい事業、つまり
(1) 「オープンソース開発方式によって無償で開発されているLinuxを、商用Linuxとしてパッケージ化・販売・サポートする事業」(Red
脅威を強く感じるMicrosoft社 この半年の間で最も驚かされた事件は、Microsoft社独禁法違反裁判でビル・ゲイツのビデオ証言がいよいよ上映されるという1998年11月2日、Microsoft社の社内機密文書がなぜか流出しインターネット上で公開されてしまったという事件だった。30ページにも及ぶその文書は、「Linuxという新しいOSが、Microsoft社の将来にとっていかに大きな脅威であるか、Microsoft社はそれをどう叩くべきか」についての分析資料であった。この資料は、流出時期が、ハロウィーンの時期と重なったため、通称ハロウィーン文書と呼ばれる。 前掲論文「オープンソースとは何か」の中で、オープンソース開発方式の理論的支柱となったのがエリック・レイモンドによって書かれた「The Cathedral and the Bazaar」という論文で、山形浩生氏による邦訳(「伽藍とバザール」)をインターネット上で読むことができるとご紹介したが、またまた同じく山形氏の尽力で、このハロウィーン文書も、インターネット上で日本語で読むことができる。興味のある読者の方はぜひ目を通していただきたい。 さらに、Linuxが一躍メジャーストリームに躍り出たことは、Microsoft社独禁法裁判でも話題となっている。「情報技術産業における独占状態とは、あくまでかりそめのもので、ずっと継続する保証はなく、新規参入者に一気にシェアを奪い取られる脅威は常に存在しているのだ。だからなりふり構わぬ競争をしていかなければならないのだ」というMicrosoft社の論理を正当化するのに、Linuxの台頭は間違いなく一役買っている。
ビル・ゲイツは、今年2月、ドイツの雑誌のインタビューに、 ちなみにゲイツの回答の中に出てくるPalmは、米国で既に「事実上の標準」とまで言われるほど普及する携帯オーガナイザのPalm Pilotのこと。 Symbianとは、Nokia、Ericsson、Motorolaのセルラーホン・トップ3社とイギリスのPDAメーカのPsion が共同出資したベンチャー企業のことである。 そしてまたまた今年に入ってから起こってきた新しい動きが「Windows料金返還運動」である。 現在ほぼすべてのパソコンが、Windowsを標準装備して販売されているわけだが、当然、Windowsの料金は、パソコンの価格に織り込まれている。つまり、パソコンを購入した時点で、Windowsを使う使わないに関わらず、ユーザはWindowsの料金を支払っていることになる。Windowsしか選択肢がなかった時は仕方ない。でもLinuxという選択肢が出てきた以上、Linuxだけを使いたい人には、未使用のWindowsに支払った費用を返還してほしい。こういう論理で、この「Windows料金返還運動」が始まったのである。 「Windows Refund Center」というWebサイトを訪れると、どうしたらこの運動に参加できるのが詳細に記載されている。「パソコンを箱から開けたら、Windowsを起動せずに、Linux等の他OSのブートディスクを挿入してそのOSを立ち上げて、Windows料金返還を要求しよう」と主張する。 次から次へとよくもまぁ、新しいことが起きるものである。
オープンソース・これからの注目点 では、そのことを踏まえて、オープンソース関連で、これからの注目点を最後に挙げておくことにしよう。
(1) Linuxは、デスクトップ領域でも認知されるようになるか? 何かとてつもなく面白いことが起こるとすれば、それは新しいオープンソース型ソフトウェア開発プロジェクト・Wineから凄い成果が出た時に限られるという気がする。このプロジェクトは、スイスのアレキサンドル・ジュリアード氏(28歳)によって主導され、約150名のオープンソース開発者が参加している。 Wineの「Win」は、Windowsの「Win」。「e」はEmulatorの「e」。開発しているのは、Windows・エミュレータである。つまり、Linuxの上にこのWineをかぶせれば、Windows上で動くアプリケーションがすべてLinux上で動くようになるという代物だ。現在のWineはまだまだ未熟で、とても産業界にインパクトを与える存在からはほど遠い。しかし化ける可能性だってあるから要注目だ。
(2) Linuxにおけるオープンソース開発体制は今後も盤石か? 果たして世界中にどれだけの数の潜在的オープンソース開発者が存在するのか、開発者が膨れ上がった時に現在の開発体制の良さが保たれるのか、などなど興味深い点がたくさんあり、要注目だ。
(3) 顧客はLinuxを信頼するか? それが、冒頭でご紹介した3タイプの新事業、「商用Linuxパッケージ販売・サポート事業」(Red Hat Software社ら)、「Linux用データベースの販売・サポート事業」(Oracle社、IBM社、Informix社)、「Linux標準装備PCの販売・サポート事業」(Dell社、Compaq社、HP社ら)の登場によって、果たしてこの不安が解消されて、顧客がLinuxコミュニティ全体に対して「信頼」(Trust)を持つのかという問題である。これは(2)のポイントとも深く関係する。 この「信頼」は突き詰めていけば、「Microsoft社員開発者フルタイム数百人+同社のサポート体制」に対して置いていた信頼と同程度の信頼を、「世界中のボランティア開発者パートタイム数千人+いろいろな会社のサポート体制」に対して置くことができるかという問題である。これも容易には解の出ない難しい問いだ。しかしそれだけにこれからの要注目ポイントだと思う。 ただいずれにせよ、「Linuxとオープンソース」に勢いがついてきたことは疑いようもない事実だ。サーバ市場へのインパクトだけだってはかりしれない。1999年も引き続き、「Linuxとオープンソース」は、何かと新しい話題を提供し続けていくに違いないのである。 ■
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ページ先頭へ | ||||||||||||||
| Home > The Archives > コンセンサス | ||||||||||||||
|
|
|
© 2002 Umeda Mochio. All rights reserved. |