 |
|||
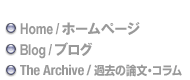
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||
|
|
[対談] 田中直毅 VS 梅田望夫 2001年8月20日[日経ビジネス]より
現場主義を貫くエコノミストとシリコンバレーに立脚するコンサルタント、2人の論客は過酷な大競争時代の到来と、その帰結として社会の二極化を予想。 日本の潜在力は高いが、世界と戦える人材の育成には新たな夢が必要と訴える。(司会は日経ビジネス編集長、野村 裕知) ――今日は、日本人と日本社会の在り方について語っていただきたいと思います。工業化社会の建設に成功した日本が、ポスト工業化社会を迎え国際競争力の低下が指摘されています。まずは、日本の現状をどう見るかからお願いします。 田中 日米を比較した時、米国社会の変化の激しさと、日本のもたつきを一番感じるのが教育ですね。 1990年代に入って、米国の教育達成度が上昇しました。国民の平均在学年数は70年代、80年代とほとんど横ばいだったのが、90年代に急速に上がった。これは一体どういうことだ、と米国で教育経済学を研究する知人に聞くと「企業の人材ニーズが変化した反映だ」と言う。これまで中学校卒業の人に任せていた仕事に高校卒業の人を採用したい、高卒の人の仕事に大卒を、と様々な職業分野で企業の要求水準が一段上がった。 そうなると、例えば高卒の人は、自分の仕事を大卒の人に奪われ、より給与の低い仕事へと追いやられる。それではかなわないから、コミュニティーカレッジに通い、情報処理など仕事に役立つ知識を身につけようと、歯を食いしばって勉強をし始めたわけです。 梅田 確かに、米国では社会人向けの講座は盛況です。 田中 子どもたちの学習の方法も大きく変わっている。先生が与えた課題に対して、子どもたちはCD-ROMに収められた百科事典やインターネットを駆使して、自分で調べ、専門家に質問し、どんどん深く学んでいく。ところが、日本では依然として、あらかじめ決まっている履修範囲を、特定の教材や指導法に基づき子どもたちに教えている。そのうえ、円周率が3.14では計算できない子どももいるから、3にしましょうなんてことまで言い出す。 一方、例えばインドという国は、極めて高水準の数学教育を土壌に、毎年30万人ものソフトウエア技術者を生み出している。こうした状況を見ると、日本社会は完全に流れの外に取り残されたのではないかと感じます。 梅田 米国に住んでいる者の実感としては、平均の底上げよりも、二極化の進展を感じます。米国社会の二極化と言うと、まず収入面での格差拡大が話題になりますが、その前には、勉強する人と勉強しない人のデバイドが存在する。米国企業が人種や国籍など一切考慮せず、能力とコストの関係だけで人を雇用する傾向を強めたためですね。米国企業のこうした動きは海外にも影響を及ぼしている。 私もインド人と一緒に仕事をしていますが、何しろ人口が多いから、彼らの受験戦争は日本の比ではないらしい。彼らのレジュメには高校時代の成績順位まで書いてあって、ある年に生まれたインド人全体の成績順位のようなものが明確に分かる。その一番上位の層が米国に来る。中国がやや遅れてインドと同じ道をたどっていますね。 最近、マサチューセッツ工科大学(MIT)が授業教材の無償公開を始めました。今後10年で講義ノートから宿題、推薦資料まで全面的に公開する。想像するに、中国やインド、あるいは東欧などの優秀な学生は、MITの決断に歓喜しているのではないでしょうか。自国での教育に満足できない極めて優秀な連中がMITの教材を使って競争を始める。その一部は米国に留学し、さらに激しい競争を続ける。35歳くらいまでの世界中の俊英が頭脳の大競争を繰り広げる。そんな時代の到来を感じます。 ――日本の工業化成功の背景には、国際的に高い日本人の教育水準があったと指摘されます。だが、ポスト工業化社会においては、一国の全体的な平均水準はあまり意味を持たないということでしょうか。 梅田 世界に50億の人間がいるとして、工業化社会において日米欧の約5億人が高い生活を享受してきた。それ以外の9割の人たちは、たとえ能力が高くても、日米欧の平均的な労働者よりも低い生活水準を甘受しなければならなかった。 仮にIT(情報技術)革命によって工業化社会から知能社会への転換がもたらされるとすれば、徹底的に学んだ人、自己研鑽を積んだ人とそうでない人の間に、国という概念を超えた形でデバイドが起こるのではないか。様々な肌の色が交じり合うシリコンバレーで仕事をしていると、そうした未来への予感を感じるのは確かです。 田中 NASA(米航空宇宙局)のエンジニアの4人に1人がインド人。シリコンバレーのスタートアップ企業の2割は中国人が創業していると言いますよね。 梅田 今はもっと多いかもしれません。 田中 はっきりしているのは、各国の最も優秀な連中を受け入れ、競わせる土俵を米国が作り、その上に乗って戦おうという人間がどんどん集まっている事実です。そういう土俵を作ろうと考えたこともなく、また、土俵に乗ろうとせず、ベタ降りに降りてしまった社会との格差はあまりに大きい。 ――この格差を埋める手だてをどう考えますか。 梅田 学校が円周率を3で教えようが、本当に数学が好きで優秀な子どもなら、自分で円周率とは何なのか独習していくと思う。そのための環境はインターネットをはじめ、十分に揃っています。だから、初等教育をそう深刻に考える必要はないと思います。米国の小学校だって崩壊していますからね。 いわゆる一流大学に合格する人たち、というのは、確かにかつての学生ほど勉強してこなかったかもしれないが、ポテンシャルという面ではかつてと今とでそんなに差があるはずはない。彼らに対して高等教育の段階で徹底した競争原理を働かせれば、キャッチアップは可能ではないでしょうか。 田中 東京大学の先生方で、教育の現状にものすごい危機感を持った人たちが、今熱心に取り組んでいるのが高校生相手の出張講義なんです。例えば、ある時は仙台に行って、その地域の数学や物理の成績最優秀の生徒たちを集め、講義をする。「その子たちを東大に呼ぶためなの」と聞いたところ、そうではないと言うんです。「別に東大に来なくてもいい。本当に能力がある子どもたちに刺激さえ与えられればいい」と言う。10人集めれば、そのうち2人か3人は、短時間の講義がきっかけになって知的な刺激を受け、猛烈に食いついてくるそうです。「適当な時期に適切な刺激さえあれば、伸びる人間は自分で伸びていく」という考え方ですね。 梅田 これまで日本の教育は平均を底上げすることを暗黙のうちに皆が目標にしてきた。この先生たちのように、上をさらに伸ばす、というのを口だけでなく実行すれば、効果は大きいはずです。僕は、日本の場合、潜在能力を持つ層は分厚いと思っています。でなければ、今のハイテクに支えられた日本の産業構造はあり得ないはずです。 ――平均の底上げから上位層のさらなる引き上げという思想転換を迫られているのは教育だけでなく、日本の企業社会にも当てはまりそうです。 梅田 その通りで、僕は日本企業の経営者に「社内にドリームチームを作ってください」と言っている。社員5万人の大企業でも、例えば、特定のテクノロジーに関してずば抜けた知識と能力を持つ人材はせいぜい5人くらいです。しかし、人事部にはその5人を選抜してチームを組ませるという発想はありませんでした。組織内の格差はなるべく小さい方がよく、平均値を引き上げることで組織全体の力を高める、という発想です。 もうこれでは、世界的な競争に生き残るのは難しい。特に、財務やテクノロジーなどの先端分野では、個人の能力差は極めて大きいだけに、最優秀な人材の能力をフルに利用しなければならなくなっている。生き残りへの危機感の強い企業ほど、こうした考え方を実行に移し始めていると感じます。 ――個人のずば抜けた能力が組織のパフォーマンス全体を左右する、というのは日本企業がこれまであまり考えてこなかった状況かもしれません。 田中 これは、様々な分野における状況の複雑化の産物でしょうね。我々、エコノミストの業界では、ここ20年ほどで経済を分析する際の変数がどんどんと増えてきた。かつての日本におけるカッコつきのケインジアンのように金融にはまるで無関心でも経済を語れた時代ではもうない。今、経済を分析しようとすれば、金融はもちろん、グローバルな産業のネットワークに通じていて、米国社会のリズムが体感でき、ITもその本質を理解していなければならない。その意味でエコノミストのトレーニングはものすごく難しくなっている。 梅田 僕も正直に白状すると、専門とするIT分野の技術進歩が早すぎて、だんだん分からなくなってきています。ここ十数年の先端科学技術の進展を考えると、ITにせよ、バイオテクノロジーにせよ、最先端知識を常にキャッチアップして、その部分で仕事のできる人というのはごく限られてくる。先端分野は、そこそこ優秀な人たちがグループで挑み、流した汗の総量で成果が決まる、という世界ではなくなってしまった。 ――「ITの振興による活力ある新産業の創出」なんて簡単に言いますが、そんな生やさしいものではない? 田中 この先に待ち受けているのは、遊園地なんかにある回転ゴンドラのような世界じゃないかな。ゴンドラをつかんで走っているうちに、スピードが上がってくると、遠心力によって、足が地面から離れてゴンドラに振り回されるような形になる。どんどん加速する中で、振り落とされないように鉄棒をぎゅっと握らなければならない。日々、力を強め続けないと、脱落してしまう。そんなイメージです。 ――だとすると、産業構造の改革には何らかの受け皿が欠かせません。しかし、その具体像が見えてこない。 梅田 受け皿とは違いますが、やはり日本企業が株主志向の経営を徹底させ、きちんとした利益体質を取り戻さなければならないと思います。少子高齢化が進む中、日本人がこれまで蓄積した富を失わず増やしていくためには、預貯金や年金の投資先である強い日本企業が存在しなければ話にならない。それに加えて、デフレによる生活コストの低下。この2つの組み合わせしか、社会全体が回っていく状況は考えにくい。収入面での二極化が先に進行した米国の場合、基本的な生活コストの安さがセーフティーネットとして働いていると言える。IT化とグローバリゼーションは必然的にデフレを引き起こすから、生活コストの低下は実現していくのではないでしょうか。 田中 生活費が高いままの二極化は、様々なものを剥奪された、という感覚を生じさせる。生活費を徹底して低下させる仕組みが働けば、かなり違ってくるでしょうね。確かに自家用ジェットを所有する人は羨ましいが、誰もが自家用ジェットの生活を幸せと感じるかと言えば…。 梅田 そっち側の人たちは、ますます過酷な回転ゴンドラに挑まなければならない。 田中 一方で、普通に働いていればカローラが買えるという選択肢がある。十分に下がった生活費の中でそこそこの暮らしができるのであれば、それでいいのではないかな。よく指摘されるように、これがそんなに不安定な社会だとは思わない。まあ、たまには自家用ジェットにも乗せてもらいたいと思うけどね(笑)。 ――「100人のビル・ゲイツを生む」という政策目標よりは、はるかにリアリティーはあります。 梅田 2つの選択肢を許容する社会なら、自然と100人のビル・ゲイツが生まれてくる。そうとも言えるんだと思います。 ――そのためには、過酷な競争に挑む動機が問題になってきます。 田中 米国社会で奮闘する中国人やインド人と日本人の差はハングリーさだと思うね。中国にせよ、インドにせよ、まだまだ貧しいですから、昨日と違う明日への夢は大きなインセンティブとして機能する。 梅田 では、これまで豊かだった日本人はどうすればいいのかですよね。 確かに、中国人やインド人の猛烈な努力の背景にはハングリー精神があると感じる。日本人が同じものを原動力にするのが無理だとすれば、豊かさがもたらす余裕を逆に生かすべきだと思う。取りあえず食べていく心配は脇に置いといて、自分が愛する物事を極める、という形で世界に太刀打ちできる人たちを輩出したとしても全く不思議ではない。大リーグに挑んだイチロー選手なんてその典型ではないですか。 田中 そう。今必要なのは新しいストーリーなんだと思う。それを夢と呼んでもいい。日本社会は旧来とは違う新しい夢を必要としている。ここ何年も、その夢を作ることに失敗してきた。だから、今日本社会に求められているのは、どういう夢、どういう物語を作り出せるかという一種の創作能力なんだと思いますね。 梅田 日本に戻ってきて驚くのが、日本のプロ野球よりも、イチロー選手や新庄選手の活躍に皆が熱中していることです。彼らの挑戦は、明らかに、旧来にない新しいストーリーでしょう。あれが日本人が見たがっている夢の1つの姿だとすれば、日本社会に変化の兆しありだと思います。
■
|
|
|
|
||
| ページ先頭へ | ||
| Home > The Archives > 日経ビジネス | ||
|
|
|
© 2002 Umeda Mochio. All rights reserved. |