 |
|||
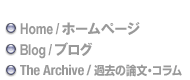
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||
|
|
インターネット時代のビジネスの覇者は 1996年3月4日[日経ビジネス]より
昨年秋のComdex以来、インターネット利用を主目的とする低価格機器の提案に注目が集まっている。「500ドル・PC(パソコン)」とか「インターネット・ステーション」とか「WEB BOY」とか、人によってまだ呼び方もまちまちという段階であるが、ハードディスクを持たず、ウィンテル・アーキテクチャー(ウィンドウズとインテル・チップはPC産業における税金と言われ始めた)にしばられなければ、500ドル程度で商品化可能というのである。主提唱者はサン・マイクロシステムズ、オラクル、IBMの3社である。大型商品が生まれる可能性としてだけでも大ニュースなのだが、その背景にはもっと深い部分で、コンピューター産業全体を大きく揺るがす構想が隠れている。 これまでのPC産業というのは「1人PC1台」を究極の目標として発展を続けてきた。しかしこれからは「PCのような機器」を「一人が複数台持ち」「世界中のすべての機器が相互に超高速ネットワーク接続される」時代がやってこようとしている。ネットワークが超高速化していくと、PC1台の中で情報をやり取りする速度(ハードディスクへのアクセス速度)も、ネットワークを介して情報をやり取りする速度もほぼ同じになるというポイントだ。自分のPCのハードディスクの中に保存してある情報も、ネットワーク上の情報も同じスピードでアクセスできるので、PC側の機能は限りなく軽くてもよくなり、ハードディスクさえ持たなくてもよいはずだという論理が「500ドル・PC」提案の背景にある。 「1人1台」を目指してきたため、これまでのPCは技術革新の枠を1台の中に詰め込み続けてきた。その結果、プロセッサーのスピードは速くなり、メモリー容量・ハードディスク容量は増加の一途をたどり、OSの機能は拡張し、搭載するアプリケーションソフトの数も増え、CD-ROMまでも搭載されるようになった。機能増強が自己目的化した感も否めないPCに対するアンチテーゼとして、「500ドル・PC」は提案されたのである。
「ウィンテル」の隆盛は終わる? 第3世代はどんな時代になり、誰が業界を支配することになるのか。IBMが第1世代を、マイクロソフト、インテルが第2世代を支配したのと同じ構造は、果たして第3世代にも当てはまるであろうか。当てはまるとするならば、支配者は誰になるのだろう。また支配者たるためには、今何をすればよいのだろう。コンピューター産業をリードする米国企業経営者の頭の中は、こうした問に答えていくためには、世代交代のありかについての2つの仮説を徹底的に考え抜く必要がある。
世代交代仮説A
世代交代仮説B 94年10月に私は日本からシリコンバレーに引っ越してきたのだが、その当時シリコンバレーで盛んに行われていた世代交代議論の大勢は仮説Aの支持であり、マイクロソフトの影響力ここまで極まったかと、かなりのショックを感じたのをよく覚えている。マイクロソフトの業界支配に対する「諦め観」が産業全体を覆っていた。 しかし95年4月頃から、明確な技術的な裏付けを伴って、仮説Bが勢いよく台頭してきた。「マイクロソフト、インテル、憎し、羨まし」という感情論の域を越えた、第3世代のコンピューティング・スタイル全体に関わる議論が起こり始めた。そして、今は拮抗状態か、または仮説B支持の声のほうが大きくなってきたのである。1年余りで変われば変わるものと驚くとともに、産業の行く末を左右する力強い技術開発が深く密かに行われていたことに、畏敬の念すら覚える。 そんな世代交代という光源を「500ドル・PC」または「インターネット・ステーション」に当ててみれば、それらがまさに仮説Bにおける「PCではない第3世代のハードウエア・プラットホーム」だと理解できるはずである。「PCではない」機器に「PC」の名を冠する「500ドル・PC」という呼称は誤解を招くので、次節からは「インターネット・ステーション」と呼ぶことにしたい。
「インテリジェンスの集中点」を押さえるものが勝つ 「インターネット・ステーション」は、PCに比べて低機能低価格である。ハードディスクを持たないから「インターネット・ステーション」側に「インテリジェンスの集中点」は生まれてこない。必要なプログラムやデータは、必要な時に「ネットワーク」から供給されてくるイメージである。そうなると「インテリジェンスの集中点」が、端末側からネットワーク側に移ることになる。「インテリジェンスの集中点」がネットワーク側にと言うのは少し曖昧で、実際にはネットワークの中に存在するサーバーに移行するのである。 「インターネット・ステーション」を強く提案しているのがサン・マイクロシステムズ、オラクル、IBMの3社であることにここで改めて思いを馳せれば、なるほどこの3社はサーバー企業であり、真の狙いはサーバー側に「インテリジェンスの集中点」を持たせることであり、そこを押さえて第3世代を支配したいのだと、理解できるのである。 マイクロソフトを中心とする第2世代勢力が「インターネット・ステーション」勢を、「中央集中処理の時代に逆戻りさせようとする時代錯誤的試み」と非難しているのは、こういう背景からである。せっかく「インテリジェンスの集中点」が中央にではなく、ユーザーの手元に移ったのに、それを取り上げるとは何事か。取り上げようとしているのは、第1世代の亡霊たちではないかという主張である。IBMが単年度の業績を回復しただけでなく将来に向け自信を取り戻しつつあるのも、この世代交代議論と無関係ではない。「インテリジェンスの集中点」という意味において、第1世代と第3世代の親和性が極めて高いからなのである。
どんなコンピューターもOSも関係なく動くのがJava インターネットが世界的大ブームとなり急激に多くの人々の関心を集めたのは、WWW(ワールド・ワイド・ウェブ)へのアクセスが簡単に行えるようになったからである。情報(データ)がWWWに関連する標準に基づいて作られていさえすれば、それが世界中のどこにあろうとも、ブラウザー(例えばネットスケープ・ナビゲーター)を使って、どんなコンピューターからでもアクセスできるようになったためである。つまり「情報(データ)へのアクセス」が標準化された瞬間から爆発的普及が始まったと言い換えてもよい。結果として、「情報(データ)がネットワークの中を自由に動いていくこと」が可能となった。これがWWW革命の本質である。 これに続く第2段階として、「プログラムがネットワーク中を動いていくこと」の標準化を目指すのがJavaである。現在でもWWWからプログラムをダウンロードすることは可能であり、「プログラムがネットワークの中を動いていくこと」は部分的に実現されている。しかし現在のプログラムはすべて、ウィンドウズ用とかマック用とか任天堂スーパーファミコン用、動作するコンピューターの構成やOS(基本ソフト)を意識して作られている。つまりプログラムをダウンロードするといっても自分の使っているコンピューターは何で、OSのバージョンは何で、といったことを常に意識しなければならない。自分の使っているコンピューターに合わないプログラムはダウンロードしても使えない。「情報(データ)へのアクセス」もWWW革命以前は、どんなコンピューターのどんなソフトを使って作ったファイルなのかを常に意識しながらやり取りしていた。そのころの状況にとても近い。つまり、現在のプログラムについてはまだ、ネットワーク上に存在する多種多様なコンピューターの中を「自由に動いていく」というイメージからはほど遠いのである。 いったん作られたプログラムが、動作するコンピューターの構成やOSとは関係なくいつでもどこでも必ず動いてくれなければ、「プログラムがネットワークの中を自由に動いていくこと」にはならない。それを目指すのがJava革命なのである。 「一太郎」でも「ワード」でも第2世代までのプログラムは「コンパイラ」という道具を使って作られていたが、Javaは「インタプリタ」というメカニズムで動作するところに本質的な違いがある。「コンパイラ」と「インタプリタ」というのは、プログラム言語処理システムにおける基本方式の2つなのだが、こうした基本方式レベルでマイクロソフトの支配する世界に対するアンチテーゼが提起されたところにJavaの斬新さがある。 「コンパイラ」というのは、プログラム言語で記述されたプログラムを、動作するコンピューターにしか理解できない機械語コードに変換する道具である。動作するコンピューターの構成やOSを意識した機械語コードが「コンパイラ」によって作られるわけだ。ウィンドウズ用「ワード」とマック用「ワード」が全くの別製品であるのも、コンピューターのバージョンアップに合わせてソフトウエアのバージョンアップをしなければならないのも、すべてプログラムが「コンパイラ」によって作られているためである。 一方「インタプリタ」というのは、プログラム言語で記述されたプログラムを、動作するコンピューターの上で解釈しながら実行するものである。つまりJavaで書かれたプログラムは、機械語コードに変換されるのではなく、単純に言えばそのままの状態で流通し、ユーザーがプログラムを動かそうとするその瞬間に解釈されて実行される。つまり、このメカニズムならばプログラム自身がポータビリティーを持ち、「プログラムはネットワークの中を自由に動いていくこと」が可能となるのである。 ただ「インタプリタ」にはプログラム実行速度性能が遅いという大きな欠点がある。実行時に解釈実行することのオーバーヘッドが大きく「コンパイラ」に比べて格段に実行速度が遅いのである。この欠点を持つため「インタプリタ」方式は長く忘れられていた方式だった。その方式を敢えて今採用したJavaが、様々な工夫をこらしてこの欠点をどれだけ克服するか、産業界はそこに注目している。 「情報(データ)がネットワークの中を自由に動いていく」WWW革命に続き、「プログラムがネットワークの中を自由に動いていく」Java革命が現実のものとなると、それはコンピューター産業全体を揺るがす大事件となるに違いないのである。
IT産業に挑戦突き付ける「端末無料、ネットワーク有料」 米国の家電量販店に行くと、「セルラー電話・ゼロドル(無料)」という看板が目につくようになった。通信サービス・プロバイダーがセルラー電話をメーカーから買い上げ、ユーザーに無料で提供し、後に期待できる通信料で元を取ろうとしているわけである。これが「端末無料、ネットワーク有料」のビジネスモデルの極端な例である。 まず「端末無料」について考えてみよう。端末側の「インターネット・ステーション」は「無料」とまではいかないまでも「500ドル」という低価格が構想され始めた。WWWブラウザーの「事実上の標準」になりつつあるネットスケープは、早い時期から「端末無料、ネットワーク有料」のビジネスモデルを先取りして、一般ユーザー用のブラウザーは無料配布し、サーバー側のソフトウエアを有料にしてきた。端末に付属しなければならない基本ソフトウエアは、今後もネットスケープの成功にならって無料配布されることになろう。その意味でも「端末無料」または「端末の低価格化」は進行していくはずだ。そしてセルラー電話程度のコストでできる軽い端末ならば、通信サービス・プロバイダーが買い上げてユーザーに無料配布することも想像に難くない。
生活・社会をも変えるIT 最近話題のエレクトロニック・コマースにしても、米国の起業家(アントレプレナー)たちの最大の関心事は、「ネットワーク有料」ビジネスモデルをもっともっと細分化した中でどこを押さえれば最も儲かるかという点である。そこを現実ビジネスの試行錯誤の中から見つけようとしている。「ネットワーク」周辺の新規事業機会がかなり自由に追求できる規制の少ない米国市場で、通信サービス・プロバイダーも巻き込んだ形で、今後数年にわたって様々な試行錯誤が繰り返され、「ネットワーク有料」のビジネスモデルが模索され定着していくと考えられる。 「端末無料・ネットワーク有料」のビジネスモデルは、IT(情報技術)産業全体に全く新しい挑戦を突き付けることになるはずである。 これからの10年あるいは20年、ITは我々の行動様式、生活、仕事の仕方、社会の仕組みを大きく変えていくに違いない。そのインフラとしてのコンピューティング・スタイルやビジネスモデルに関わる論争や技術競争が今、まさに行われているのだと思う。今後の進展には要注意である。 「これは世代交代をめぐる10年に1度の戦いなのだろうか?」とふと自問することがある。将来が不確実で、激しく変化するIT産業の現場シリコンバレーに身を置く感覚からすると、「10年」というのは「永遠」という感じがするので、「いや、5年に一度かなあ」などと瞬間的に思い直してしまう。 しかし、一方で、自動車や電話やテレビや映画の進歩発展の歴史における基本スタイルが定まると、それ以降、基本スタイルは安定したまま技術や製品だけがどんどん進歩を続けていくというパスに入っていくことも事実である。 そんな意味で、本稿で述べてきたのはIT産業における「基本スタイル」の議論なだけに、後世の人が「基本スタイルにおける最終戦争」と名付けるところの戦いの真只中に、ひょっとしたら今立ち会っているのかもしれないなあ、などと夢想することもあるのである。 ■ 掲載時のコメント:汎用大型コンピューターを中心とした「IBMの時代」。
|
|
|
|
||
| ページ先頭へ | ||
| Home > The Archives > 日経ビジネス | ||
|
|
|
© 2002 Umeda Mochio. All rights reserved. |