 |
|||
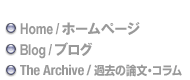
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||
|
|
Linux上でWindowsを動かす
1999年3月8日[日経パソコン]より
Linuxに勢いがついてきた。 情報技術産業において「勢いがつく」というのは、「キラキラ光る小さなモノ」の価値や存在意義が、産業全体で認知された瞬間から、巨大企業が一気にその周辺に投資し始め、もう逆戻りすることができないだけの大きなうねりができてしまうことをいう。 1998年が、「Linuxが全世界的に注目を集め始めた年」だったとすれば、99年は間違いなく、「Linux市場離陸(Takeoff)の年」となるだろう。 98年後半から、「オープンソース開発方式によって無償で開発されているLinuxを、商用Linuxとしてパッケージ化・販売・サポートする事業」(レッドハット社)に、インテルとネットスケープ・コミュニケーションズが出資。続いて、「Linuxサーバー用データベース」は、オラクル、IBM、インフォミックスといった主要ベンダーがコミットメントを示した。 そして99年1月、PCサーバー大手のデルコンピュータ、コンパックコンピュータ、ヒューレット・パッカードらが相次いで、「LinuxをOSとして標準装備したPCサーバー(インテルチップ搭載)を作って販売、サポートする事業」を開始すると発表した。安いモデルは2000ドル前後にまで低価格化が進むPCサーバー事業において、Windows NTのコスト(約500ドルから750ドルの間)に対する商用Linuxのコスト(約50ドル)は価格破壊そのものであり、サーバーベンダーにとっては基本的に朗報なのだ。業界を支配するマイクロソフトも、独禁法違反裁判でその行動を強く監視されているから、ネットスケープを叩き潰したときのような圧力をベンダーにかけることはできないようだ。 「Linuxは面白いと思うよ」と言いつつも「誰が責任を持ってくれるの」と不安いっぱいだった顧客も、これからは本気でLinuxサーバーの導入を考え始めることだろう。 ただこのあたりまでの話は、米国でLinuxが注目を集め始めた昨年夏頃から「半ば織り込み済み」の流れだ。順調すぎると言えなくもないが、当時シリコンバレーでイメージされていたシナリオ通りに産業界が動いている。
「Wine」プロジェクトに注目 その名はWine。スイスのアレキサンドル・ジュリアード氏(28歳)を中心に、約150人の開発者が参加するオープンソース型ソフトウエア開発プロジェクトだ。Wineの「Win」は、Windowsの「Win」。「e」はEmulatorの「e」。開発しているのは、Windowsエミュレータである。つまり、Linuxの上にこのWineをかぶせれば、Windows上で動くアプリケーションがすべてLinux上で動くようになるという代物だ。 もしこのプロジェクトが現在のLinuxのような「勢い」を持つ日がやってくるとしたら、サーバー市場だけでなく、デスクトップ市場でのWindowsも大きな脅威にさらされることだろう。 ソフトウエアエミュレータというのは、屋上屋を重ねるようなインプリメンテーションなので性能が出ない。そのうえ、雑多なアプリケーションのすべてが動くと保証することが難しく、限定的なアプリケーションをごく普通に使う範囲では動きますよ、というくらいが関の山。OSのバージョンアップごとに新しい作業が発生するから、OSの最新バージョンに追いついていくのは大変だ。これが、コンピューターサイエンスの常識である。 Wineはこの常識に挑む。 たしかに、現在のWineはまだまだ未熟で、産業界にインパクトを与える存在からはほど遠い。しかし、シリコンバレーではWineプロジェクトに資金援助しようと、草の根で金集めを始めた人もいる。 ネットの世界とシリコンバレーではどんなことだって起こり得る。 新しいけれど未熟な存在に出会ったとき、私は必ずこの言葉を噛みしめて、安易にネガティブな結論を出さぬよう自戒する昨今である。 ■ 掲載時のコメント:まだコンピュータ科学者を目指していた18歳の頃に、もしLinuxやWineのようなオープンソース型開発プロジェクトが存在していたとしたら、きっと私は参加していただろう、と最近よく思う。
|
|
|
|
||
| ページ先頭へ | ||
| Home > The Archives > 日経パソコン | ||
|
|
|
© 2002 Umeda Mochio. All rights reserved. |