 |
|||
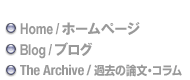
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||
|
|
米国が凄み発揮するのは逆境の時
2003年1月22日[産経新聞「正論」欄]より
不況乗り越えハイテク産業が復活へ着々と進む新技術の仕込み ドッグイヤー(七倍速)と称されるほどの猛スピードで疾走していた九〇年代後半の米国ハイテク産業は、二〇〇〇年のIT(情報技術)バブル崩壊によって失速。そしてその調整にもがく真っ只中で、二〇〇一年九月十一日の同時多発テロに直面し、さらに大きな打撃を受けた。それから十六カ月が経過し、ようやく米国ハイテク産業に落ち着いた雰囲気が漂い始めた昨今である。
水面下ではイノベーション創出のための不断の営みが続き、新技術の仕込みが着々と進んでいることが、将来への拠り所となっている。米国の財産とも言うべき「イノベーション創出のための壮大な社会システム」は、バブル崩壊後の今も、きちんと機能し続けているのである。 「研究開発行為によって新しい技術が生まれてから、その技術が大きく花開き、社会に根づいて経済成長に貢献するまでのプロセス」というのは、日本の場合「一企業内の閉じた空間」の中で執り行われるのが普通であった。 機能する強靭なシステム しかし米国の仕組みが他国と際立って違うのは、この複雑で創造的なプロセスを「社会全体の開かれた空間」の中で廻していくという思想に基づいていることだ。 そしてそのプロセスのすみずみにまで「才能についての門戸を世界に開いてオープンでフェアな競争をさせる(世界中から才能を集め、国内に無国籍化現象を引き起こす)」という思想と「経済合理性追求のための市場原理を浸透させる」という原則が貫かれている。それゆえ、好況期は好況期なりに、不況期は不況期なりに機能する強靭(きょうじん)なシステムに仕上がっている。 このシステムの構成主体は、基礎研究を担当する大学・研究機関、基礎研究を応用して市場創造を担当するベンチャー、グローバル市場制覇を担当する大企業の三者である。最初の二つ、つまり大学・研究機関、ベンチャーが、膨大な試行錯誤を伴う「淘汰(とうた)の段階」を担当するわけだ。 そしてこの「淘汰の段階」を廻すための資金に「広義のリスクマネー」(国家予算と機関投資家によるベンチャーキャピタル投資資金)が使われ、そこに競争原理と市場原理が貫かれる。この仕組みの中で生まれた某(なにがし)かの成果は、その成果を生み出した人々とともにこの三者の間を移転すること(スピンオフや買収の日常化と人材流動)で、組織を超えてイノベーションの架け橋を築いていく。
二〇〇〇年のバブル崩壊以降、米国株式市場は相変わらず低迷を続け、公開企業は本業に特化して収益を上げるよう求められている。よって、ほんの一部の企業を除き、次なる大型イノベーションのための仕込みができない。 しかし、軍事予算を含む莫大(ばくだい)な国家研究予算と、好況時に機関投資家から調達済みのベンチャーキャピタル投資資金は潤沢なので、大学・研究機関・ベンチャーによる「淘汰の段階」は、好況時よりもゆったりとした時間の流れの中で、粛々と廻っている。 バブル崩壊後の厳しい調整過程を経て、一流の技術を持たないベンチャーの大半は淘汰された。生き残ったベンチャーからは一攫千金(いっかくせんきん)を夢見た浮ついた気分が削(そ)ぎ落とされ、自らの生命線たる技術を磨き、利益をきちんと出せるビジネスを模索するという「あるべき姿」に戻って、力を蓄えながら、米国経済全体の回復を待っている。 シリコンバレーには「不況期こそイノベーション創出のチャンス」という経験則があるが、イノベーション主体が大企業セクターに集中せず社会全体に分散されているメリットをテコに復活するのが、米国ハイテク産業の流儀なのである。 米国での生活実感も含めて言えば、米国が本当の凄(すご)みを発揮するのは、実は順調なときではなく逆境のときである。その意味で、逆境の中で久しぶりに中長期的感覚を取り戻しつつある米国ハイテク産業に、私は復活の兆しを感じ始めている。 もちろんバブル崩壊の調整はまだ終わっていないし、米国経済の先行きには相変わらず不透明な要素が多い。ただ一方で、復活のきっかけとなるはずの水面下でのイノベーションの胎動をも常に注視することが重要なのである。 ■
|
|
|
|
||
| ページ先頭へ | ||
| Home > The Archives > 産経新聞「正論」欄 | ||
|
|
|
© 2002 Umeda Mochio. All rights reserved. |