 |
|||
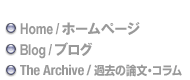
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||
|
|
IT産業の潮目が読めぬ日本勢 モノづくりの強さ過信を危惧す
2005年1月10日[産経新聞「正論」欄]より
《米国で進むパワーシフト》 二〇〇四年の米国IT(情報技術)産業は、IBMによる中国企業「聯想集団(レノボ・グループ)」へのパソコン事業売却(十二月)と、インターネット検索エンジン最大手・グーグルの株式公開(八月)という二つの対照的な出来事によって記憶されることになろう。 年に一兆円以上売り上げるIBMのパソコン事業の売却額が二千億円にも満たなかった一方、売上高約三千億円のグーグルの株式時価総額は五兆円を超えた。この差は何を意味しているのか。インターネットの「こちら側」から「あちら側」へのパワーシフトが、米国では確実に起きているのである。 インターネットの「こちら側」とは、インターネットの利用者、つまり私たち一人一人に密着したモノの世界である。パソコン、携帯電話、カーナビ、コンビニのPOS端末、高機能ATM、薄型テレビ、DVDレコーダー、デジタル・カメラ、そしてこれからは無線ICタグ。皆、インターネットと私たち一人一人を結びつけるつなぎ目の部分に用意するモノである。 インターネットの「あちら側」とは、インターネット空間に浮かぶ巨大な「情報発電所」とも言うべきバーチャルな世界である。いったんその巨大設備たる「情報発電所」に付加価値創造の仕組みを作りこめば、インターネットを介して、均質なサービスをグローバルに提供できる。 《激化する付加価値争奪戦》 グーグルをはじめとする米国インターネット企業による「あちら側」のイノベーションは、手触りのある「こちら側」のモノづくりと違って目に見えない。それだけに何が起きているのかがわからない。本紙でもグーグルについての報道は少ない。しかし米国のIT分野のトップクラスは皆、その才能の生かし所を「あちら側」での「情報発電所」の構築と見定めている。 一方、日本企業は、モノづくりを中心とした従来の強みを生かして勝負したいという気持ちが強い。だから「こちら側」のモノに、より多くの付加価値をつけることを考えて、次から次へと新しいモノを出す。モノに対して冷淡で安さに重きを置く米国の消費者と違い、モノが大好きな日本の消費者は少し高くても新しいモノを買う。よって「こちら側」の世界については、日本市場が世界の最先端を疾走し、米国市場の遅れは目を覆うばかりとなった。 ここ一、二年、「IT産業における日米の関心が明らかに違う方向を向いたな」と感ずることが多くなったのだが、それは、日本が「こちら側」に、米国が「あちら側」に没頭しているからなのである。これを現象面でだけとらえれば、日本と米国が独自の特色を生かして棲み分けているわけで、悪いことではないようにも見える。しかし事の本質はそう簡単ではない。「こちら側」と「あちら側」が、いずれ付加価値を奪い合うことになるからである。 インターネットとパソコン(あるいは「こちら側」のモノ)がつながって、私たちが某(なにがし)かの利便性を感ずるとき、その利便性を実現している主体が「こちら側」のモノなのか、それとも「あちら側」からインターネットを介して提供されてくる情報やサービスなのかということを、消費者の多くはあまり意識しないものだ。しかし、ここがこれからの付加価値争奪戦の戦場になるのである。 《日米企業分かつ未来戦略》 米国が描くIT産業の将来像は、付加価値が順次「あちら側」にシフトしていき、「こちら側」のモノはコモディティ(日用品)になる、誰でもいいから中国で作って世界に安く供給してくれればいい、というものだ。IBMパソコン事業の中国企業への売却はそれを象徴している。むろんこれから先、米国が描くシナリオ通りにIT産業が発展していくとは限らない。 ただ私が危惧(きぐ)するのは、モノづくりの強みを過信し、そこにしか生き場所がないと自己規定するあまりに「こちら側」に没頭する日本企業が、米国離れを引き起こしていることだ。違う方向に関心が向かっている米国の現在を「われ関せず」と理解しようともしていないことである。 東芝と富士通とNECの時価総額を全部足し合わせても、創業からたった六年、わずか二千七百人のグーグルの時価総額に及ばないのはなぜか。いったいグーグルとは何なのか、その台頭は何を意味するのか。本来そう問い続けなければいけない日本企業の経営者が、インターネットのことを何も知らない。米国離れを起こしている場合ではないのである。 ■
|
|
|
|
||
| ページ先頭へ | ||
| Home > The Archives > 産経新聞「正論」欄 | ||
|
|
|
© 2002 Umeda Mochio. All rights reserved. |