 |
|||
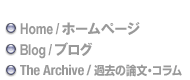
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||
|
|
ソース公開、普及に課題
1998年9月13日[日経産業新聞]より
前回に引き続き、オープンソースの話をしよう。オープンソースとは、全く新しい考え方に基づく大規模ソフトウェア開発のあり方である。あるソフトのソースコードを無料(フリー)で公開し、世界中のハッカー(優れたプログラマー)のだれもが自由に(フリー)にそのソフトを改良して再配布することを許すソフト開発方式のことである。
しかし今、注目を集めるオープンソース型ソフト、例えば、ネットスケープ・コミュニケータ、パソコン用OSのLinux、ウエブサーバーのアパッチなどは、昔のフリーソフトウェアとはスケールが全く違う。「インターネット上に散らばる世界中の膨大なハッカー資源を結びつけた大規模プログラム開発プロジェクト」の成果が、広く一般ユーザーに利用され始めているからだ。 ボランティアハッカーたちが「ただ楽しいから」と無償で気の向くままに開発したソフト作品を、マニアや学術関係者が、自分の楽しみや研究のために使っているうちはいい。しかし、一般ユーザーがビジネスのために使うとなると、全く新しい課題がたくさん生まれ、その課題を解決する新しい枠組みが必要になってくる。 「企業がオープンソース型ソフトを基幹システムに搭載した場合、だれがそのサポート責任を負ってくれるのか」「ハッカーたちは技術的におもしろい最先端ソフトの開発には興味を示すかもしれないが、ユーザー志向の混臭いソフトには興味を示さないのではないか」。オープンソース型ソフトのビジネス利用を真剣に考え始めたら、こんな疑問が次々とわいてくる。 こうした疑問のひとつひとつに対して、どんな新しいビジネスの枠組みが作られていくのか。それが今後のオープンソース動向を眺めていくポイントである。 今年の4月ころから大物ハッカーたちを中心に議論が続けられ、ハッカーカルチャーとビジネス界との間でほぼ合意が生まれたのは、まず次のようなことである。 「ユーザーインターフエース部分のソフト、ソフトのインストレーション、様々なハードヘの移植、顧客対応のシステムインテグレーンョン、サービスサポートやトレーニングといったハッカーたちがあまり興味を示さない様々な要素がなければ、ソフトは普及しない。だから、ソフトの中核部分がハッカーたちのボランティアによって無償で作られたものでも、無償のソフトの周辺やユーザーに密着したところで、こうした付加価値を付ける企業は自由にビジネスを模索して構わない」 いち早くこの流れに乗った大企業はIBMだった。6月、IBMはアパッチを同社ソフト製品群ウェブスフィアの一部として搭載すると決定し、ユーザーに対するサポートを開始した。 シリコンバレーのベンチャー企業、VAリサーチ社はインストールの面倒なLinuxをすぐに使える状態で搭載したパソコンを販売し始めた。80年代初頭のサン・マイクロシステムズの再来のようだ。 これまでボランティアで開発を続けてきたハッカーたちの中のリーダー的人物が、そのオープンソース型ソフトの周辺機能開発・販売・サポート責任を負うベンチャー企業を設立する動きもいくつか出てきた。 もちろん一般ユーザーの疑問のすべてが解決されたわけではないが、こうした新しいうねりが起こり始めたことは、その解決策がこれからひとつひとつ提示されていくであろうことを意味している。それがシリコンバレー的問題解決手法だからである。
それは「だれかにソフトを書き続けさせる強制力」の問題と言い換えてもよい。マイクロソフトのような企業の場合、プログラマーは皆、マイクロソフトからお金をもらって働く社員やコントラクターだから、当然のことながら、企業からの強制力が働く。逆にいえば、その強制力に対して一般ユーザーは費用を支払っている。信頼の源泉はこの強制力にあるわけだ。
「企業の強制力に対する信頼を超える信頼を、オープンソース・コミュニティーが一般から勝ち取ることができるのだろうか」。いずれこのことが、オープンソースを巡る最大の争点となってくるだろう。
■
|
|
|
|
||
| ページ先頭へ | ||
| Home > The Archives > 日経産業新聞 | ||
|
|
|
© 2002 Umeda Mochio. All rights reserved. |